株式会社ブルー・マーブル・ジャパンは、以下のメンバーで運営しています。業務執行の特徴は、パートナー制の体制と完全バーチャルオフィスです。パートナー制での事業執行は、案件の特徴により、適切な人材・会社等を事業パートナーとして招き、事業実施を行う業務スタイルをとっています。私たちは、一緒に仕事をする適正人材との広範なネットワークや、国内外の評価関係者やアカデミア、ソーシャルセクター(NPO/NGO)、金融関係者など広くネットワークをもっています。また、特定の事務所はもたず、国内外の事業パートナーとオンラインでのコミュニケーション、タスク・進捗管理ができる仕組みを構築して、個々人の働きやすさを大切にしています。
また、一緒に仕事をする仲間を”アソシエイト”として迎えています。現在、以下のようなメンバーとともに評価やシステム思考等の知見を使いながら、社会課題解決やそのための仕組みづくりに取り組んでいます。
今田 克司(Katsuji Imata)・代表取締役
米国(6年)、南アフリカ(5年半)含め、国内外で市民社会強化の分野でのNPOマネジメント歴25年。現在、(一財)社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ(SIMI)代表理事、(一財)CSOネットワーク常務理事を兼任するほか、以下のような肩書きを持つ。
・インパクト・コンソーシアム データ・指標分科会座長
・日本評価学会副会長、研修委員長
・休眠預金等活用法における指定活用団体である日本民間公益活動連携機構(JANPIA)評価アドバイザー
・国際協力機構(JICA)事業評価外部有識者委員会委員
・UNDP SDGインパクト基準 認定トレーナー
・TISFD (Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosure) Asia Pacific Regional Council メンバー
・Blue Marble Evaluation Advisory Council 委員
・B Lab (B Corp 認証を司る米国非営利団体)Regional Standards Advisory Group – Asia 委員
・アメリカ評価学会(AEA)Social Financeワーキンググループメンバー
CSOネットワークで「発展的評価」研修(伴走評価エキスパート事業)、日本NPOセンターで「事業評価コーディネーター」研修の評価研修プログラムを開発・実施。NPO・ソーシャルセクターを端緒に、あらゆるセクターに「役に立つ評価」の評価文化やインパクト・マネジメントを根づかせる試みを続けているほか、個社単位そしてシステム単位のインパクト投資やインパクト測定・マネジメント(IMM)の潮流や具体的なノウハウについて、海外の識者・実践家との意見交換を続けている。

千葉 直紀(Naoki Chiba)・代表取締役
社会的インパクト・マネジメント/IMM(インパクト測定・マネジメント)および評価を軸として、ソーシャルセクター(NPO/NGO/ソーシャルビジネス)、ビジネスクター(大企業/中小企業)、金融セクター、パブリックセクターなどを広く渡りながら、社会の諸課題が解決されるような実務支援(社会的インパクトを創出するための戦略構築や評価伴走支援)や人材育成(IMM研修や評価研修)を得意としている。社会的事業に関する評価のあり方や認証制度等に関する国内外の調査を広く行ってきている。
CSOネットワークでは発展的評価(Developmental Evaluation)の日本への導入研修事業(伴走評価エキスパート育成プログラム)や、社会的インパクト・マネジメント研修(一般社団法人インパクト・マネジメント・ラボ)の開発を担当。
・一般社団法人インパクト・マネジメント・ラボ 共同代表
・社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ(SIMI)事務局
・日本民間公益活動連携機構(JANPIA)評価アドバイザー
・CSOネットワーク 評価事業コーディネーター
・日本評価学会会員
・中小企業診断士(経済産業大臣登録)
・認定ファンドレイザー(日本ファンドレイジング協会)

大澤 望(Nozomu Osawa)・アソシエイト
株式会社大沢会計&人事コンサルタンツ代表取締役、一般社団法人インパクト・マネジメント・ラボ共同代表。早稲田大学公共経営大学院修了(公共経営修士)。社会的価値の創出を目的とする様々な分野の事業の調査・評価に携わるほか、評価ツール開発やガイドライン策定などの実践支援や評価文化醸成にも注力している。日本評価学会認定評価士。日本民間公益活動連携機構(JANPIA)評価アドバイザー。

清水 亜希子(Akiko Shimizu)・アソシエイト
国際開発の分野で約15年間の実務経験を通して、多岐にわたるセクター(保健、教育、社会福祉、水資源、エネルギー、運輸交通、防災等)の協力事業に従事。
国際協力機構(JICA)や外務省が実施する技術協力プロジェクトに参画したのち、JICA本部(評価部およびジェンダー平等推進室)での勤務を経て、現在は評価コンサルタントとして、国際協力事業の評価や関連調査・分析業務に携わっている。
近年は、国内において民間企業や非営利セクターが実施する事業に対し、社会的インパクト評価やプログラム評価の支援にも取り組んでいる。
- イーストアングリア大学大学院・国際開発学部にて「インパクト評価」修了
- 日本評価学会認定評価士
- 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパンのメンバー

津崎 たから(Takara Tsuzaki)・アソシエイト
評価アドバイザー・評価の哲学研究者。
米国ウェスタン・ミシガン大学大学院学際的評価学博士課程に在籍中。
日本の画一的な教育に疑問を抱き、15歳で単身海外留学。高校・大学・大学院時代をスイス、米国、英国で過ごし、文化人類学、国際政治学、社会政策、組織経営を学ぶ。インドやネパールでの教育活動、国連機関、NGO/NPO、ソーシャルファイナンス、研究機関(大学・大学院等)、民間企業等、国内外のさまざまな分野・領域でプロジェクト推進に携わった後、研究者に転身。産官学民の4つのセクターで20年以上のキャリアを積んだ経験から、人材育成や評価アセスメントの開発、研修・教育事業、地域医療、地域政策、組織マネージメント、多文化共生事業等評価アドバイザーとして活動する。通訳・翻訳業やバイリンガルエグゼクティブコーチとしても活躍中。
詳しいプロフィール:https://note.com/invalue/n/nfcb9fc6fb326
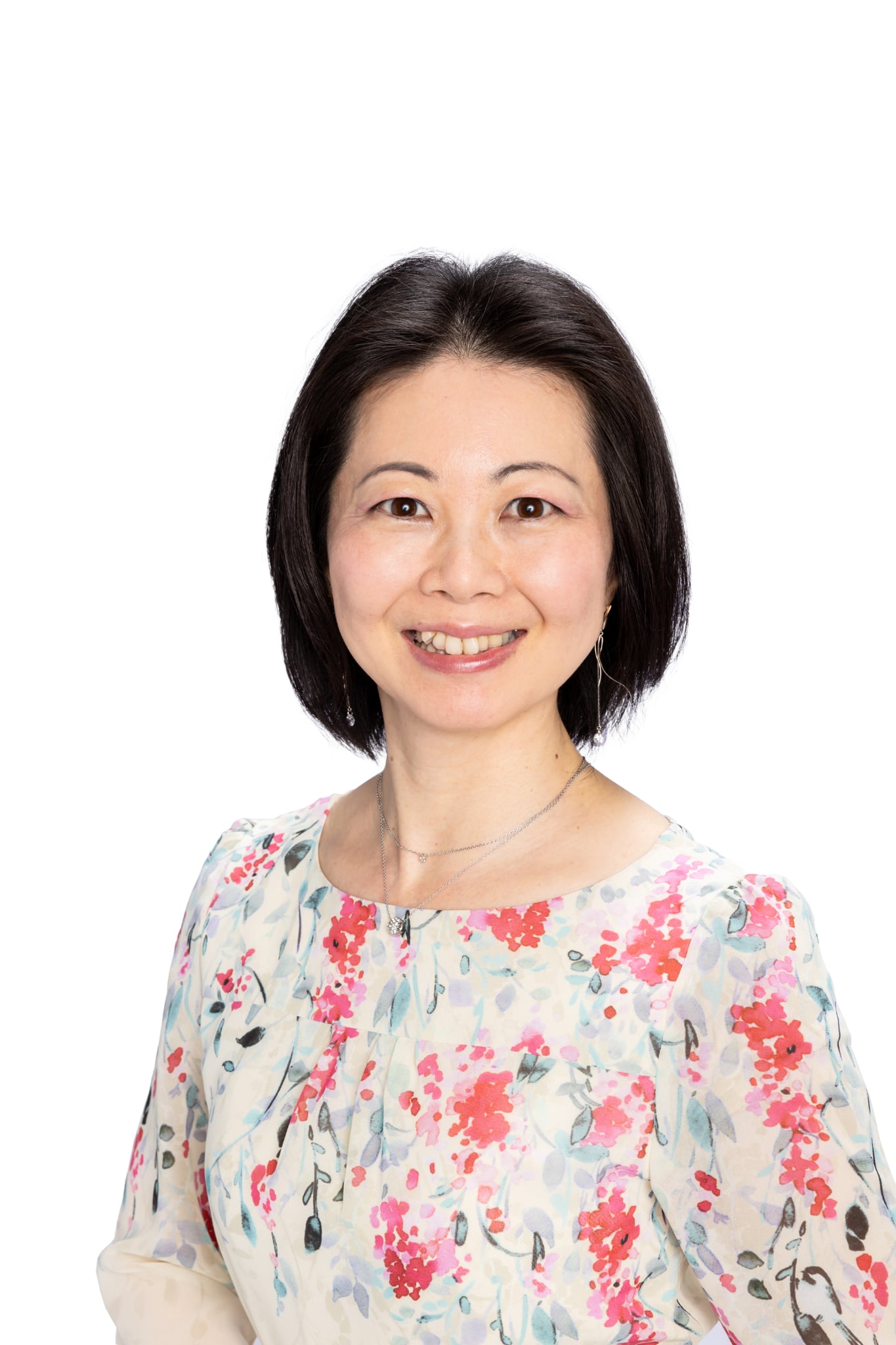
中谷 美南子(Minako Nakatani)・アソシエイト
評価コンサルタント、チームやまびこ案内人。国連職員・開発コンサルタントとして国際協力案件の評価に多数従事した後、東日本大震災を機に公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの緊急復興支援事業の事業モニタリング・評価を担当。2017年の独立以降、子ども若者支援、文化芸術、地域開発、人材育成、コレクティブ・インパクト等の領域の評価に従事する。評価の実践を社会改善の「場づくり」の一環として、日本社会により普及されることを目指している。専門分野は、発展的評価、実用重視の評価、評価能力強化、事業モニタリング評価制度の構築等。日本評価学会認定評価士。日本評価学会評価士養成講座の講師(「評価可能性アセスメント」2022年~現在)。
評価業務以外では、NPO法人きづくにおいて、子ども支援の現場で子どもの権利侵害を予防する「子どものセーフガーディング事業」の設計と推進を担当。

渡辺 眞子(Mako Watanabe)・アソシエイト
岐阜県出身・名古屋市在住。NPO・NGOの伴走支援・事業評価支援、就業・福祉・教育分野における新規企画立案・プロジェクトマネジメントに取り組む。
大学卒業後、就業支援NPOにて求職者や企業への支援を経験したのち、新規事業立案・プロジェクトマネジメントに従事。大型の助成金を活用した事業にて社会的インパクト評価業務を担当したことが契機となり、日本評価学会認定評価士を取得。
2020年より、NPOの中間支援組織にてSIBを活用した就労支援事業のプログラム管理ならびに評価業務、社会的インパクト評価案件、NPO/NGOへの組織基盤強化支援を担当。
現在は、評価コンサルタントとして、NPOや企業における社会的インパクト評価やIMMに関する支援を行う。
